こんにちは!
トモタメです。今回は、初めて同じ本で2回に分けて書評をしてみます。
個人的に興味が強かったのと、おそらく転職を考えている方は、おそらくこの4つの基準で選んでいる方が大半だと思ったからです。
しかしながら、この本ではその4つの基準を仕事選びの大罪として主張しております。
なぜ、これらの基準が大罪なのか一緒に見ていきましょう!
一緒にこちらも見ておくと、仕事選びは万全です!
尚、実際の本では7つの大罪と書いておりますが、今回はトモタメが絞って紹介いたします。
このブログを読んで欲しい方
・転職をしようと考えている方
・今の仕事を続けようか悩んでいる方
このブログを読んでわかること
・仕事選びに基準にしがちな4つの基準が、なぜ、大罪なのかが分かります。
・自分の転職の仕方の見直しができ、行動に移しやすくなります。
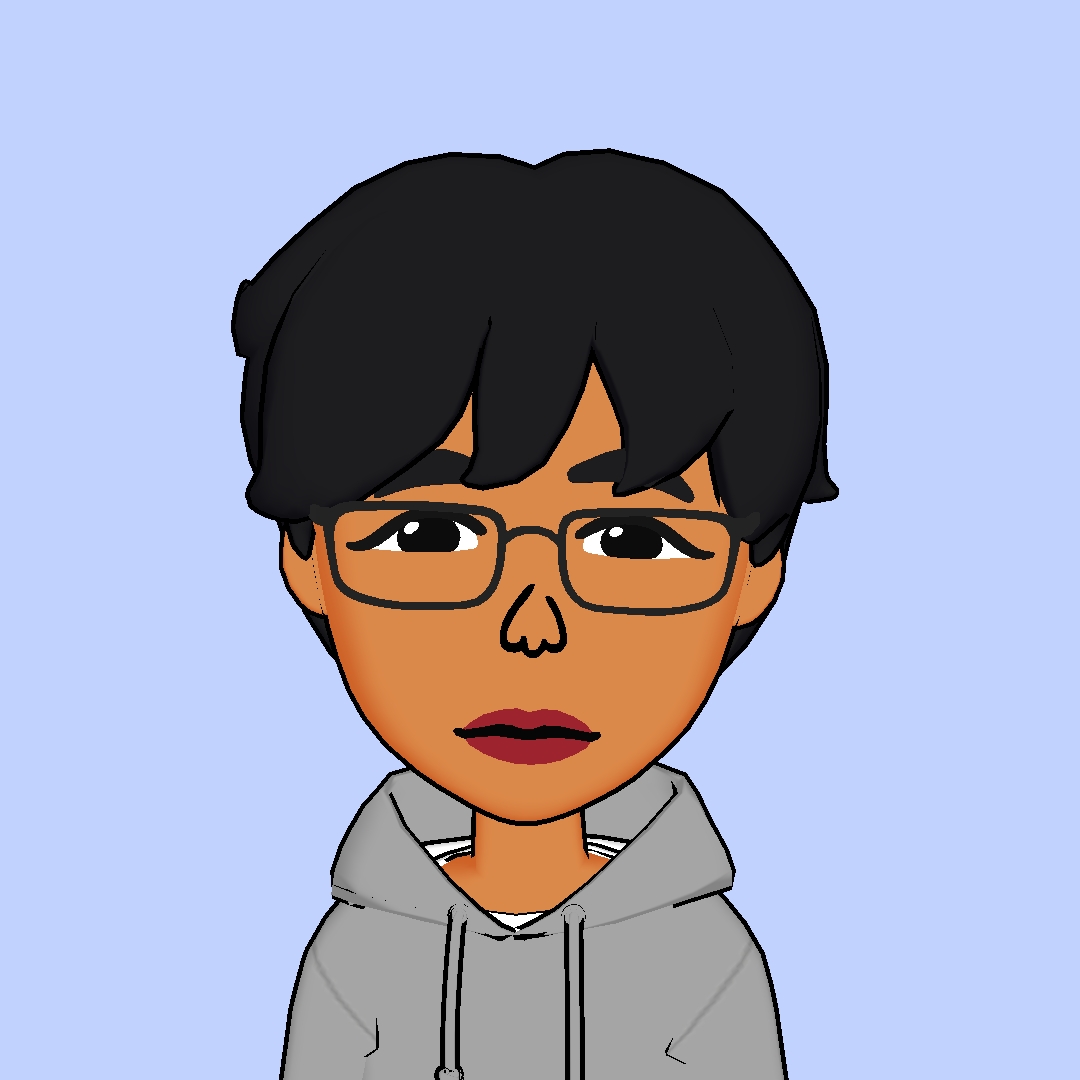
では、一緒に4つの基準について一緒にみていきましょう!
仕事選びの基準にしてはいけない4大罪
好きを仕事にする
理由は好きなことを仕事にしようが、しまいが最終的な幸福感は変わらないと実験結果で出ているからです。
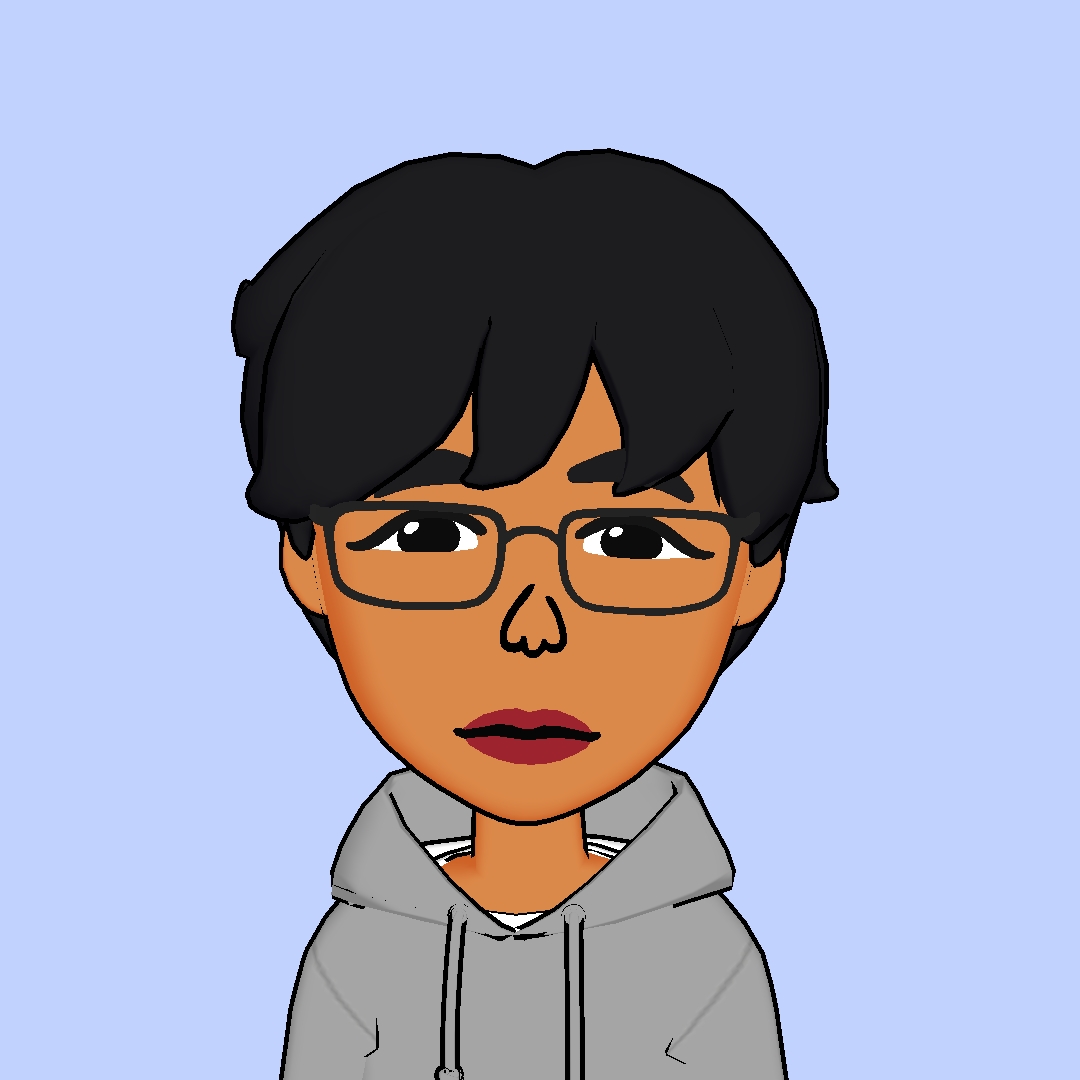
え、これは転職のときは基準にしてそう・・・
どういう実験をしたんだろう?
実験:2015年にミシガン大学が「好きなことを仕事にする人は幸せか?」というテーマで調査
方法:数百を超える職業から聞き取り調査を行い、仕事の考え方が個人の幸福にどう影響するか調査
被験者の「仕事観」を2パターンに分けました。
適合派:好きなことを仕事にするのが幸せだと考えるタイプ
成長派:仕事は続けるうちに好きになるものだと考えるタイプ
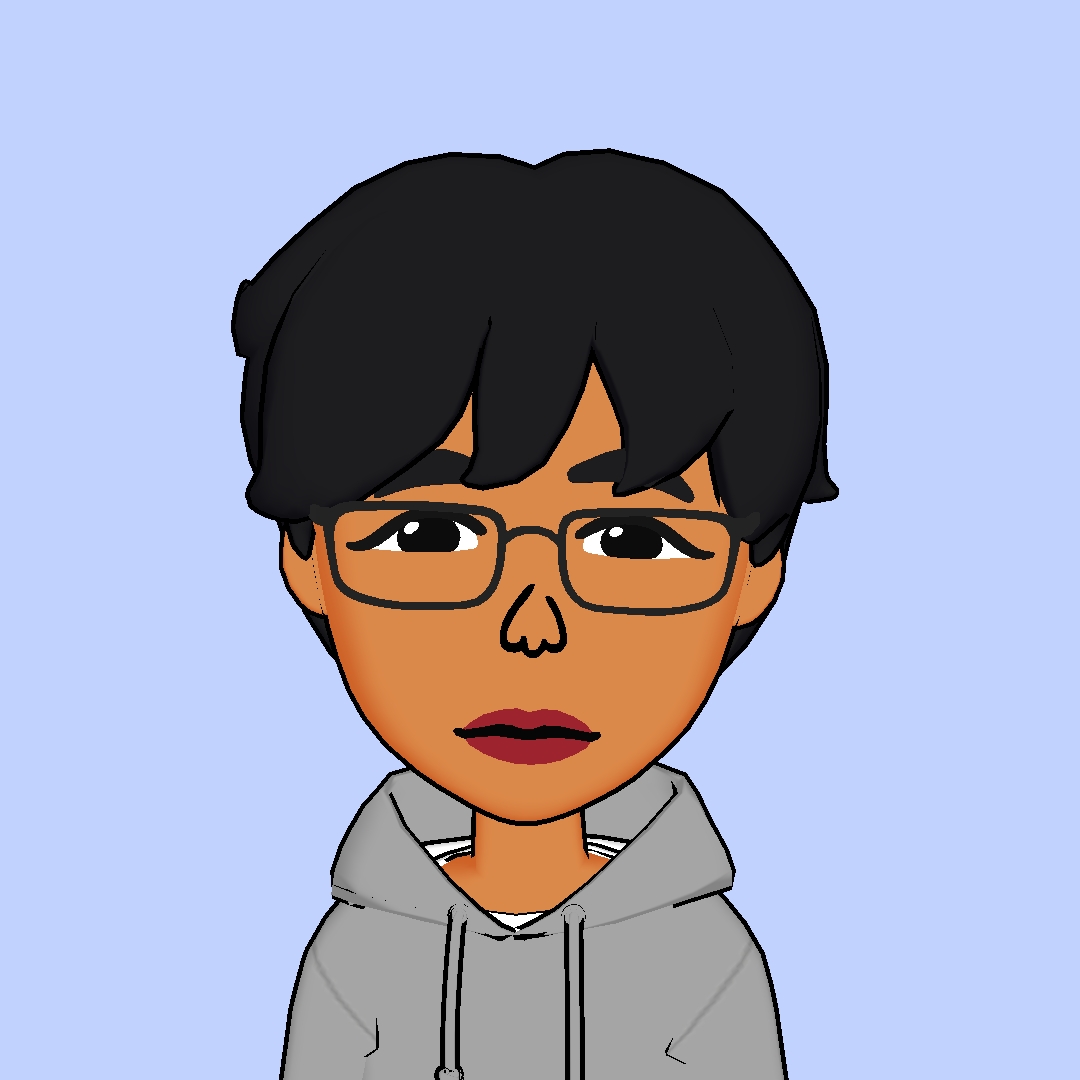
実験の結果はどうなったんだろう?
結果:適合派の幸福度が高いのは最初だけ
1から5年の長いスパンで見た場合、両者の幸福度・年収・キャリアなどのレベルは成長派の方が高かったそうです。
他の大学でも同じような実験をしていますが、好きなことを仕事にしている人の実験結果はあまり良くなかったとのことです。
これらから考えられることは、仕事を好きになるかどうかはやってみないと分からないし、自分が注いだ時間や労力の量に比例するということです。
「なんとなくやってたら楽しくなってきた」
このような感覚を持てたら、真の天職かもしれません。
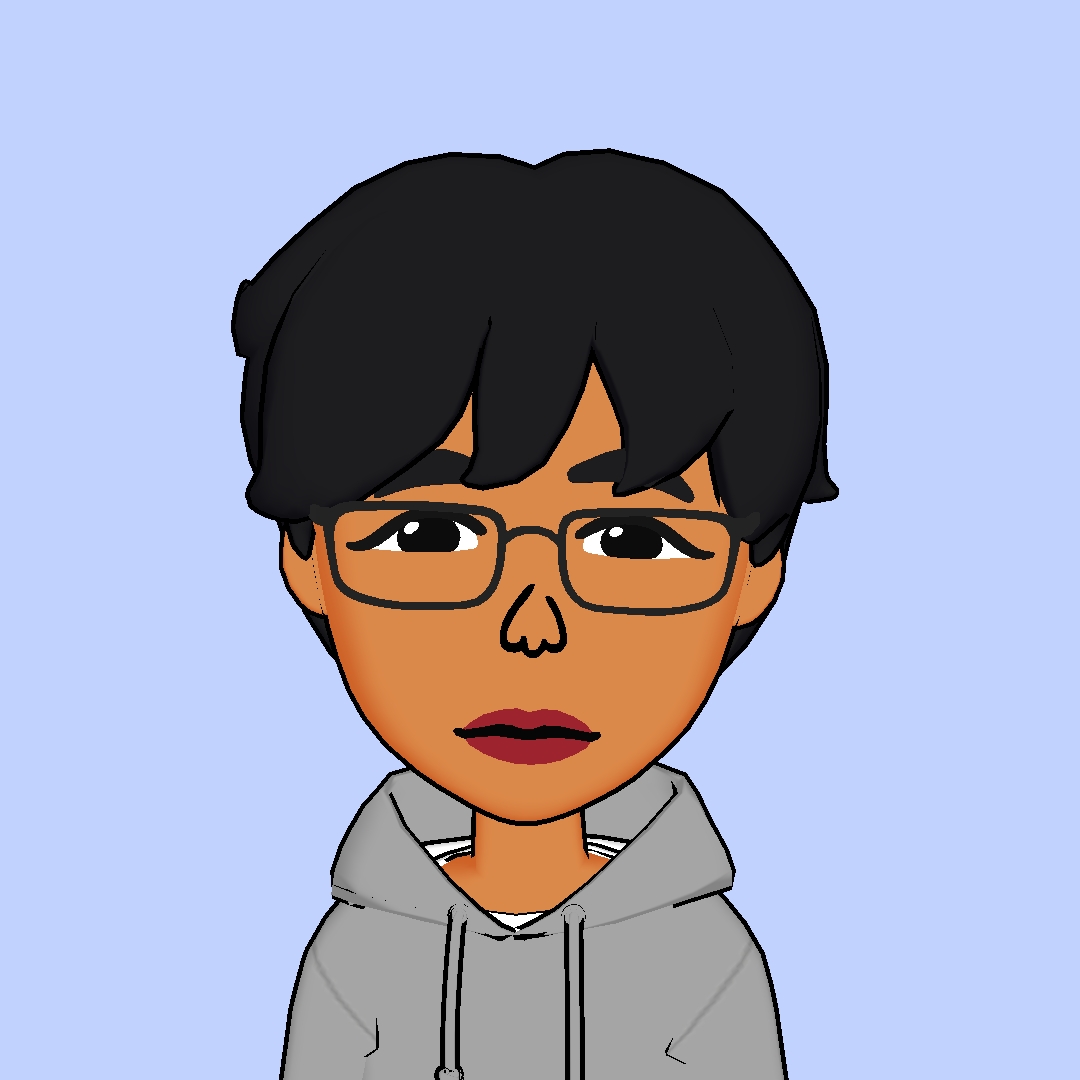
実際に僕も仕事の就活のイメージと実際に働き始めてからのイメージは全く違う
給料の多さで選ぶ
これも基準にしてしまう人は多いかもしれません。
給料の多さと幸福度は比例しないのでしょうか?
結論から言うと、給料の高さと幸福と仕事の満足度と関係が無いです。
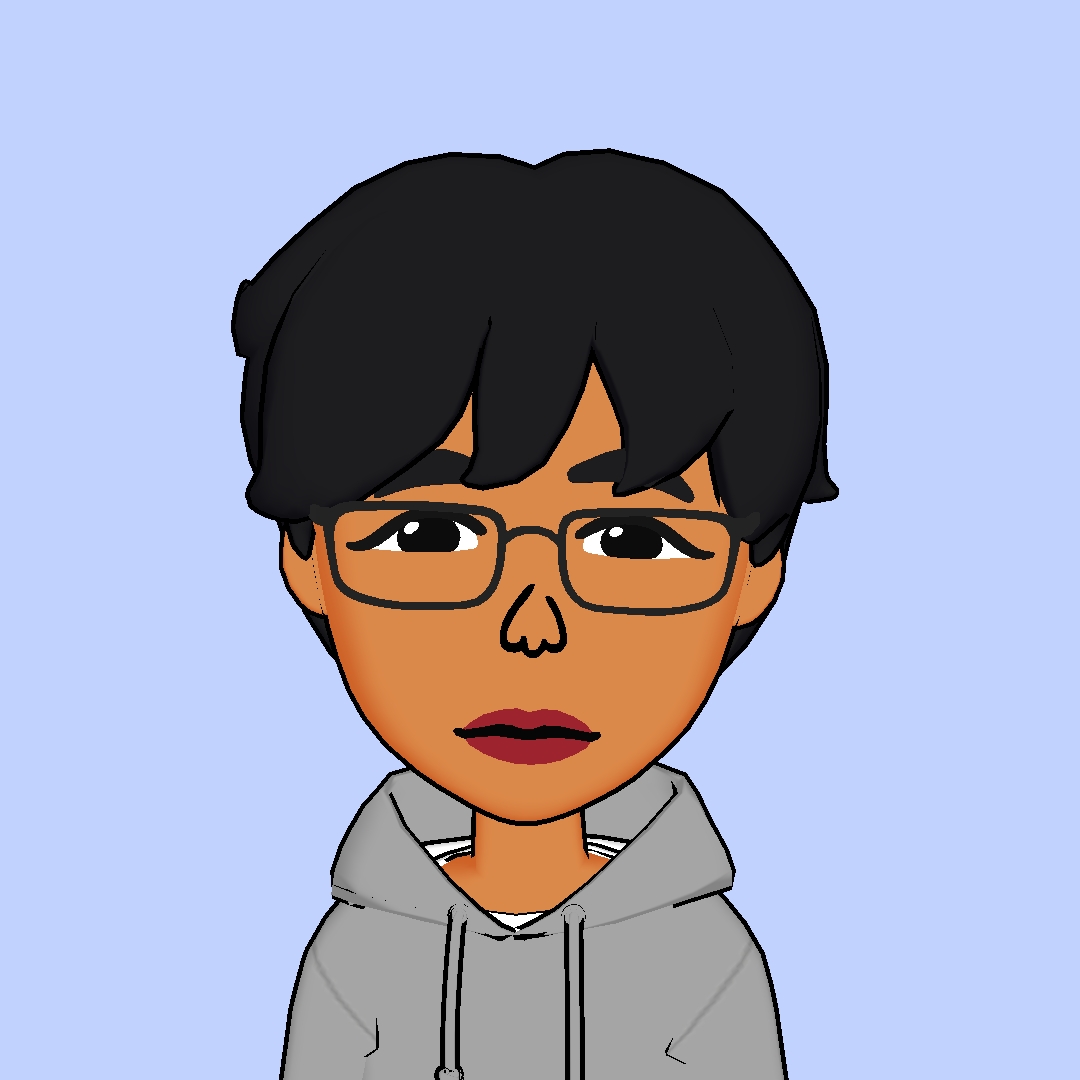
でも、多くの給料をもらうために転職を考える人が多いよね?
確かに一時的な幸福度は上がりますが、その幸福度の上昇は平均して1年しか続かないことが実験の結果で出ています。
3万5000件の年収データを分析したバーゼル大学の調査によれば、たいていの人は給料がアップした直後に大きく幸福度は上がり、その感覚は1年まで上昇を続けます。
しかしながら、1年を過ぎた後から幸福度は急降下を始め、3年もすればもとのレベルまで戻ります。
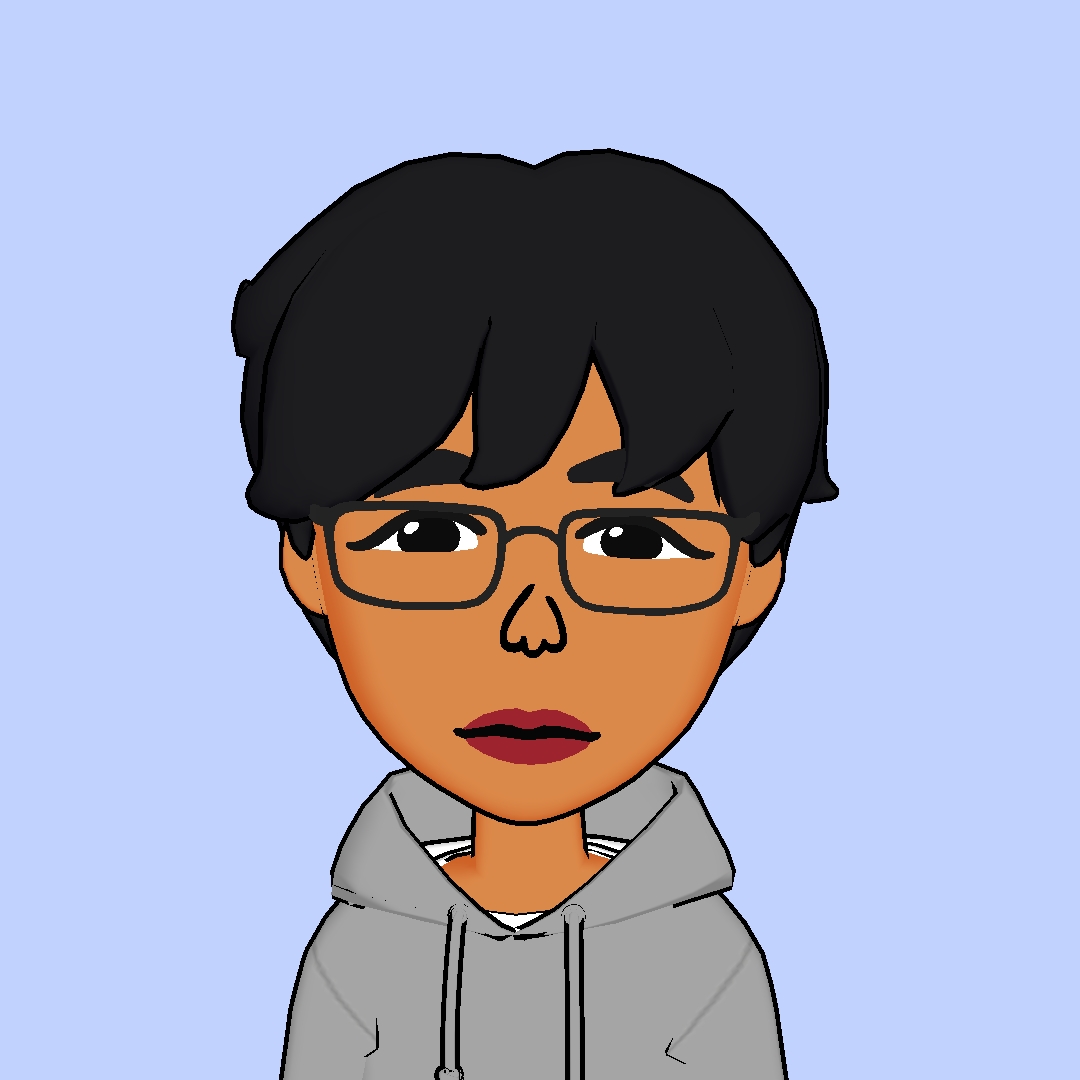
じゃあ、毎年年収が上がり続ければ幸福度は上昇し続けるということ?
そのように上がり続けることは無いです。
ノーベル受賞者であるダニエル・カーネマンの研究によると
「年収が800~900万円に達した時点で幸福度の上昇は横ばいになる」
と言われています。
また、日本を含む世界140か国の収入と幸福度を相関した研究では、こんな結果が出ています。
年収が400万円から430万円を超えた場合、そこからさらに幸福度を5%上げるには追加で400~430万円必要になる。
以上の実験結果から考えられることは、年収を基準に選んで仕事を選んだ場合、一定の年収までは幸福度は上昇するかもしれないが、長期的に見るとあまり関係ないということです。
適性に合った仕事を求める
強みを活かせる仕事を選んでも人生の幸福度には関係が無いです。
理由は2点あります。
1点目は強みと仕事の満足度に相関があるが、その相関はとても小さいからです。
2点目は自分と同じ強みを持った同僚がいる場合、仕事の満足度が下がるからです。
2点目の理由を少し解説します。
人は他人と比較したり、他人から評価されることで幸福度に影響を受ける生き物です。
もし、同じ強みを持った同僚がいる場合、評価されるのは、自分ではなく、同僚が評価される可能性があるからです。
同僚が評価された場合、自分は評価されないので人生や仕事の幸福度は下がります。
このように、自分の強みを活かして仕事を選ぶことは周りの人の強みによって、自分の幸福度に影響が出てくるので、適切ではないです。
ただ、自分の強みを活かして仕事をすることは満足度を向上する報告は多数あるので、あくまで仕事を選ぶ基準として自分の適性はあてにしない方が良いです。
業界や職種で選ぶ
これをあてにしてはいけない理由は2点あります。
1点目は専門家であっても有望な業界は予測することが出来ないからです。
ペンシルバニア大学の研究によれば、1984年~2003年にかけて学者やジャーナリストなど248名の専門家を集めて3年~5年後の企業や経済、政治状況の予測をさせたところ2800超のデータのうち50パーセントしか当たっていないとのことでした。
つまりコイントスと同じです。
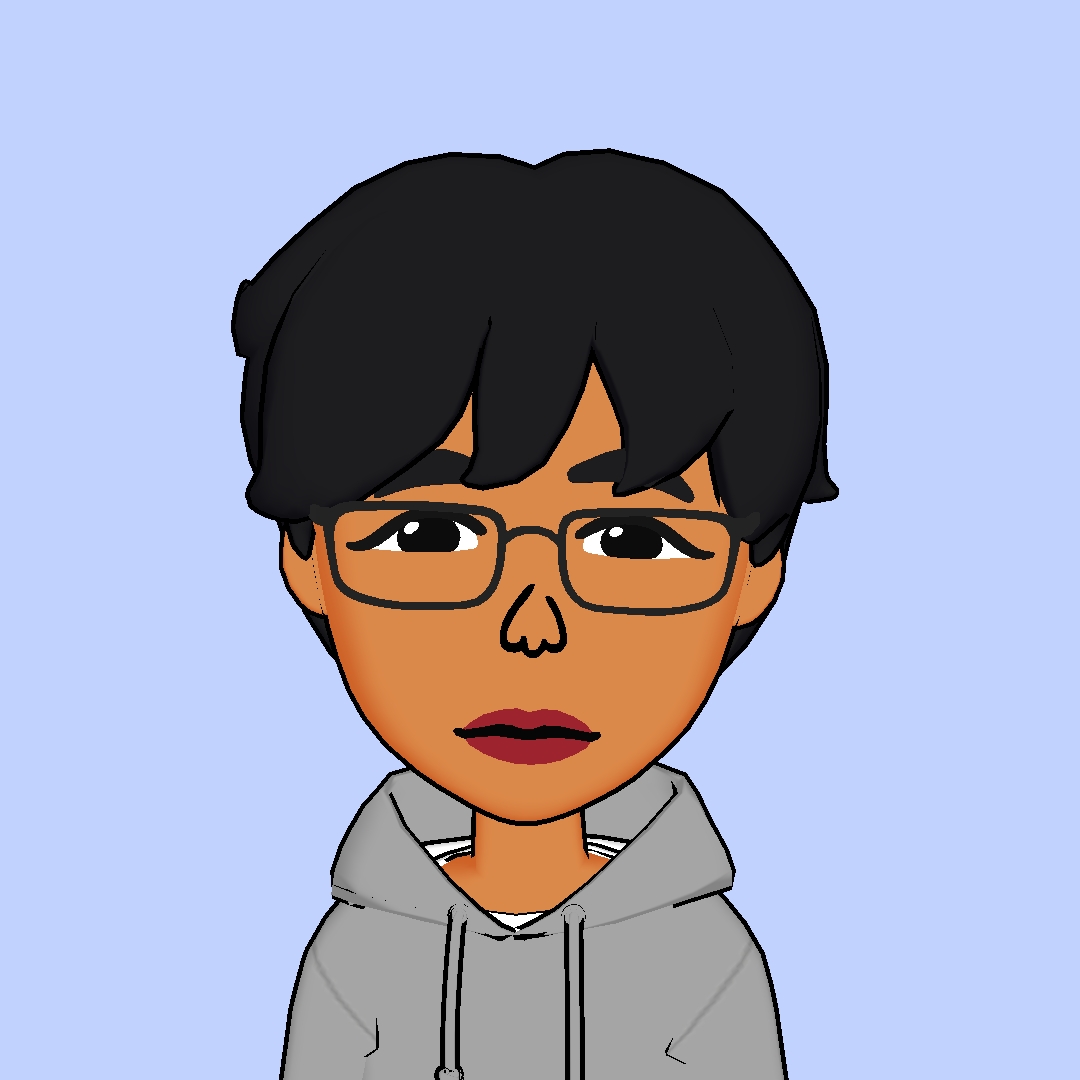
この研究のデータが今よりも18年ほど昔のことだと考えると、ITが進歩した現在は今後の伸びる業種を予想するのはもっと難しいと思うなあ・・・
2点目は人間は自分の興味の変化も予測することが出来ないからです。
私、トモタメも10年前に書評ブログを書いているとは予想していなかったです。
当時は高校生で部活三昧で読書を全くしていなかったので(笑)
正直、今後の2~3年後すらも何をしているのか全く予想できないです。
当然好みや嗜好は今後10年後何をしているかの予想なんてもってのほかです。
このように全く当てに出来ないものを適職の選びの基準にするのは、やめておいた方が良いと思います。
まとめ
これまで満足のいく仕事選びにやってはいけない4つの大罪を見てきましたが、いかがでしたでしょうか?
➀好きを仕事にする
②給料の多さで仕事を選ぶ
③適性で仕事を選ぶ
④業種・職種で仕事を選ぶ
転職や就活の際の参考になれば嬉しいです!
それでは!


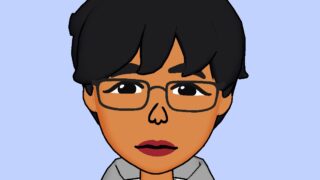





コメント